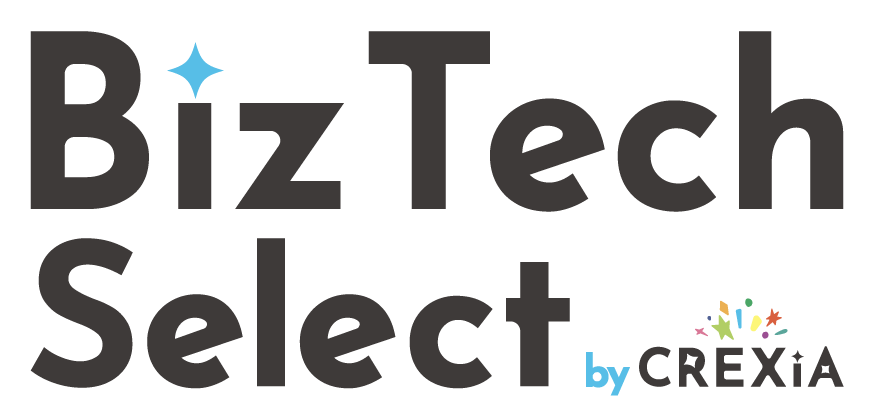マーケティングの成果を高めるうえで注目されているのが、診断コンテンツです。
診断コンテンツを活用すれば売り込み感なく見込み客の情報を獲得でき、SNSでの拡散による認知度向上も期待できます。
しかし「診断コンテンツは専門知識がないと作れないのでは?」と不安に思う方も多いでしょう。
そこでこの記事では、診断コンテンツ作成ツールを9選、無料・有料ツールを含めて紹介します。診断コンテンツを作成し、自社ブランドの認知度向上や売上拡大につなげましょう。
診断コンテンツ作成ツールおすすめ9選

それでは、おすすめの診断コンテンツ作成ツールを9選ピックアップして紹介します。
- 診断クラウド「ヨミトル」
- Makko
- Judge
- Interviewz
- 診断メーカー
- Lステップ
- クロワッサン
- ImStar
- 診断スタジオ
診断クラウド「ヨミトル」

| 料金プラン | 月額5万円〜 |
| リード獲得機能 | ◯ |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | ・Webhookによるデータ連携に対応 ・Google Analytics、Adobe Analyticsなどの分析ツール、CRMとのリアルタイム連携が可能 |
| デザインのカスタマイズ性 | 幅広い業種対応のテンプレートを用意 |
| 無料トライアル | ◯ |
| 公式サイト | https://shindancloud.com/ |
診断クラウド「ヨミトル」は、診断コンテンツの作成・実行・効果検証のサイクルを最短距離で加速させるツールです。開発不要のノーコード実装でありながら、企業が希望する複雑なロジックを自社で運用できる点が大きな特徴です。
特に、企画段階からサポートが充実しており、toCからtoBまで幅広い業種に対応した豊富なテンプレートが用意されています。さらに、AIが質問や診断軸の設計をサポートしてくれるため、効率的な企画作成が可能です。
作成したコンテンツは、JavaScript・HTML・PHPの3種類から選ぶだけでコードが発行されます。設置したいサイトに貼り付けるだけで、簡単に埋め込みが可能です。管理画面では診断利用者の個人情報に加え、利用回数や離脱率などのマーケティング成果も可視化できます。
Makko

| 料金プラン | 月額3万円〜 |
| リード獲得機能 | ◯ |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | – |
| デザインのカスタマイズ性 | ・ノーコードで直感的にカスタマイズ可能 ・ボタンカラー、フォント、背景画像などの設定項目が豊富でCSS適用もサポート ・フローチャート方式や点数方式の設問作成も柔軟に可能 |
| 無料トライアル | ◯(期間は要問い合わせ) |
| 公式サイト | https://ma-kko.com/ |
Makkoは、直感的なUIとノーコードでのデザインカスタム性に優れている診断コンテンツ作成ツールです。明確な基準がある検定やクイズに適した点数方式と、回答に応じて設問を分岐させられるフローチャート方式の2種類のロジックに対応しています。
デザイン面ではボタンカラーや背景画像などを簡単に設定できるため、自社のブランドイメージに合わせたデザインを短時間で実現可能です。作成した診断コンテンツはURL化でき、CMSへもコードをコピペするだけで簡単に設置できます。
アプリのような感覚でコンテンツを圧倒的なスピードで公開でき、Webプロモーションやリード獲得施策にすぐに組み込めます。
Judge
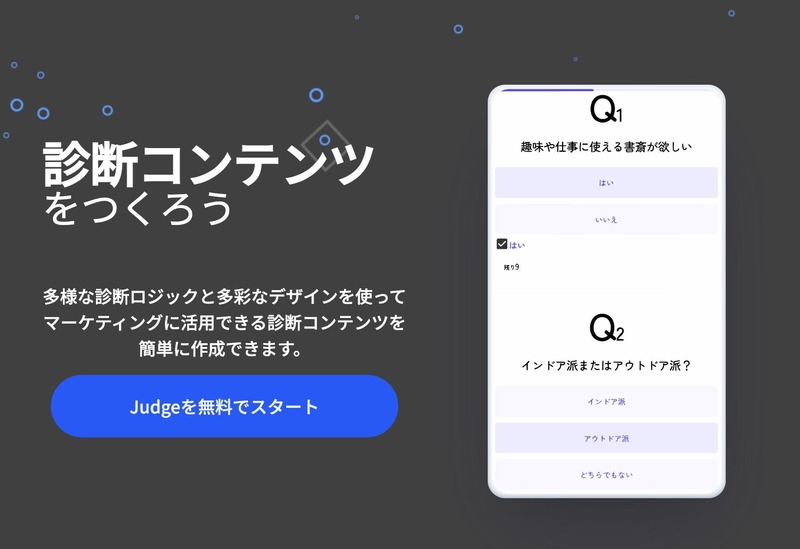
| 料金プラン | ・フリープラン:0円 ・スタンダードプラン(月額):2,800円 ・スタンダードプラン(年額):9,800円 |
| リード獲得機能 | ◯ |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | Google Analyticsとの連携が可能 |
| デザインのカスタマイズ性 | ・豊富なデザインテンプレートがあり、商材のイメージに合わせて簡単に差し替え可能 ・ウェブサイトへの埋め込みも対応 |
| 無料トライアル | – |
| 公式サイト | https://judge-hub.com/ |
Judgeは、多様な診断ロジックとアクセス数の従量課金がない完全定額制の診断コンテンツ作成ツールです。Judgeは導入ハードルの低さが魅力で小規模な診断であればコンテンツの作成は無料であり、最短10分程度で公開できます。
また、Judgeの強みは複雑な条件分岐に対応できる点です。複数選択や数値入力などの豊富な選択肢ボタンを設定でき、入力された内容に基づいて診断結果を分岐させられます。
多くのツールが2〜5種類の分岐ロジックであるのに対し、Judgeは10種類に対応している点も特徴です。
Judgeは「月◯回まで配信、それ以上は従量課金」などの制限がなく、完全に定額で利用できます。
Interviewz

| 料金プラン | ・ライトプラン:月額30,000円 ・スタンダードプラン:月額50,000円 ・エンタープライズプラン:要問い合わせ |
| リード獲得機能 | ◯ |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | HubSpot、Salesforce、Googleスプレッドシート、Slack、Google Analytics、Google カレンダーとの連携が可能 |
| デザインのカスタマイズ性 | CSSカスタマイズとHTMLタグ埋め込み対応で、自社ブランドに合わせたデザイン調整が可能 |
| 無料トライアル | ◯(30日間) |
| 公式サイト | https://lp.interviewz.io/ |
Interviewzは、診断体験・ヒアリングのDX実現に特化した診断コンテンツ作成ツールです。
Interviewzはタップのみで直感的に操作できる診断コンテンツであるため、回答率の向上を図れます。Interviewzでは、単独軸・複数軸・16タイプなど多様な診断ロジックからオリジナルの診断コンテンツを作成が可能です。
Webサイトだけでなくアプリ、メール、チャットなど様々なチャネルで利用できる拡張性の高さも特徴です。特に、利用シーンごとに最適なフローテンプレートが用意されており、最短1日での導入が可能です。
診断メーカー

| 料金プラン | 無料 |
| リード獲得機能 | – |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | X、Misskey、Mastodonなどの外部サービスとのログイン連携が可能 |
| デザインのカスタマイズ性 | ・診断タイプ(名前診断、分岐診断など)の選択と基本的なテキスト、結果設定が可能 ・イラストや文章作品の投稿機能もあり、シンプルなカスタマイズが中心 |
| 無料トライアル | – |
| 公式サイト | https://shindanmaker.com/ |
無料で手軽に始められる診断メーカーは、SNSでの拡散を狙うマーケティングにぴったりの診断コンテンツ作成ツールです。名前診断や分岐診断などの診断コンテンツを簡単に作成でき、テンプレートも充実しています。
診断メーカーは一切の料金がかからず、誰でもオリジナルの診断コンテンツを投稿・共有できるため、コストゼロで認知拡大が可能です。ただし、リード獲得機能や分析機能などマーケティング機能はありません。
Lステップ

| 料金プラン(税込) | ・フリープラン:無料 ・スタートプラン:月額5,000円 ・スタンダードプラン:月額21,780円 ・プロプラン:月額32,780円 |
| リード獲得機能 | ◯ |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | 外部連携設定でAIツールなどと連携が可能 |
| デザインのカスタマイズ性 | 回答フォームのCSSカスタマイズ、テンプレート編集(カルーセルメッセージ、画像、テキスト)が可能 |
| 無料トライアル | – |
| 公式サイト | https://linestep.jp/lp/01/ |
Lステップは、LINE公式アカウントの機能を拡張したBtoC向けMAツールで、診断コンテンツの作成機能も有しています。Lステップで作成する診断コンテンツの特徴は、LINEの非従量課金対象であるリプライメッセージを活用できる点です。配信コストを抑えながら、診断コンテンツをLINE上で拡散できます。
Lステップの診断コンテンツ作成機能は有料プランから備わっており、選択肢は最大4つまで設定が可能です。診断コンテンツの作成方法には「カルーセルを使う」「回答フォームを使う」「リッチメニューを使う」などさまざまなパターンがあります。
判定方法も、回答によって次の質問を変えていく分岐方式やポイントを加算する合計点方式など多様なロジックが可能です。
クロワッサン

| 料金プラン(税込) | ・年間プラン:月額38,500円 ・半年プラン:月額55,000円 ・3ヶ月プラン:月額99,000円 ・1ヶ月プラン:220,000円 ※初期費用:165,000円(一括払いで5万円割引) |
| リード獲得機能 | ◯ |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | LINEなど他のアプリとの連携に対応 |
| デザインのカスタマイズ性 | テンプレートを活用し、自社バナー・ロゴを設定可能 |
| 無料トライアル | ◯(期間は要問い合わせ) |
| 公式サイト | https://lp.croissant.buzz/ |
クロワッサンは、ノーコードでガチャや診断、アンケートコンテンツを簡単に作成できる診断コンテンツ作成ツールです。
クロワッサンは手軽さを追求した直感的なUIを備えており、専門知識は不要で誰でも短時間で診断コンテンツを作成可能。診断コンテンツ機能にオンラインガチャ機能を組み合わせ、ユーザーのエンゲージメントとコミュニティ活性化を図れる点も大きな特徴です。
また、データ分析が可能なダッシュボードが搭載されている点も魅力です。リアルタイムでデータを分析し、CSVダウンロードや他のアプリとの連携を通じてマーケティング戦略の立案・改善に活用できます。
ImStar

| 料金プラン | 要問い合わせ |
| リード獲得機能 | ◯ |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | ・Instagram以外のSNSやWebサイトとの連携が可能 ・YouTube、Google、Yahoo!などの広告ツールとの連携にも対応 |
| デザインのカスタマイズ性 | ストーリーズやDMに適したビジュアルデザインを直感的に調整できる |
| 無料トライアル | – |
| 公式サイト | https://n2p.co.jp/imstar/ |
ImStarは、Instagramキャンペーンを実施するためのツールであり、チャットbot機能を活用した診断コンテンツを作成できます。ImStarを利用すれば、InstagramのDM内でアンケートや診断コンテンツに回答し、応募が完了する仕組みを構築できます。そのため、ユーザーとより深いコミュニケーションを実施でき、エンゲージメントと売上貢献を目指せます。
ImStarはDMでの診断コンテンツ機能のほかに、以下のような多様なInstagramプロモーションに対応している点も特徴です。
- ストーリーズやフィード投稿を活用したインスタントウィンキャンペーン機能
- レシートマストバイキャンペーン機能
診断コンテンツを上記の機能と絡めれば、認知拡大と同時にユーザーへの理解を深められます。
診断スタジオ

| 料金プラン(税込) | ・フリープラン:無料 ・ライトプラン:月額9,900円 |
| リード獲得機能 | ◯ |
| SNS拡散機能 | ◯ |
| 外部ツール連携 | – |
| デザインのカスタマイズ性 | – |
| 無料トライアル | – |
| 公式サイト | https://sindanstudio.com/ |
診断スタジオは、リード獲得に特化したタイプ別診断作成ツールです。3軸×8結果タイプの本格的な性格診断を専門知識なしで簡単に作成できます。
また、制作画面がステップバイステップで分かりやすく、作成した診断は即座に公開が可能です。
診断コンテンツに搭載できるリード情報の入力フォームはシンプルで、ユーザーにストレスを与えません。フォーム表示設定は、ワンタッチで簡単に切り替えが可能です。
さらに、診断結果はLINEやXなどにシェアできる機能を備えており、コンテンツの自然な拡散を促進し、エンゲージメント向上に貢献してくれます。
また、回答データの詳細分析とCSVエクスポート機能により、収集したデータをマーケティング施策に活用できる点も魅力です。
診断コンテンツ作成ツールを選ぶポイント

診断コンテンツ作成ツールを選ぶポイントを5つ解説します。
- 導入ツールが目的に合っているか
- 操作性がよく直感的に使えるか
- デザインのカスタマイズ性は十分か
- 他のマーケティングツールとの連携は可能か
- 料金体系とサポート体制は適切か
導入ツールが目的に合っているか
診断コンテンツ作成ツールを選ぶ際は、「何のために診断コンテンツを作るのか」を明確にしましょう。なぜなら、診断コンテンツを作成する目的によって、ツールに求められる機能が大きく変わってくるためです。
例えば、見込み顧客の獲得が最優先事項であれば、診断結果を表示する前にメールアドレスや企業名を入力してもらう機能が欠かせません。
一方で、ブランドの認知拡大が目的なら結果をXやLINEなどのSNSでシェアできる機能が充実しているツールを選ぶべきです。自社のマーケティング戦略と照らし合わせ、目的達成のために必要な機能を備えた診断コンテンツ作成ツールを選びましょう。
操作性がよく直感的に使えるか
診断コンテンツ作成ツールを選ぶ際は、操作性がよく直感的に使えるかを確認しましょう。操作方法が複雑だと、診断コンテンツの作成に膨大な時間がかかります。
また、特定の担当者しか扱えない属人化の状態に陥るなど、診断コンテンツの運用が継続できなくなるかもしれません。
多くのツールでは、無料トライアルが設けられています。そのため、実際に管理画面を触り「これなら誰でもスムーズに診断コンテンツを作成できそうだ」と感じられるか事前に確認しましょう。
デザインのカスタマイズ性は十分か
デザインのカスタマイズ性が十分かどうかも、診断コンテンツ作成ツールを選ぶ際に確認しましょう。ユーザーが直接触れる診断コンテンツは、企業のイメージを大きく左右します。
デザインのカスタマイズ性が低いと、企業のイメージにあった診断コンテンツを作成できず、ブランドイメージを損ないかねません。
診断コンテンツ作成ツールを選ぶ際は、デザインのカスタマイズ性において以下の点を確認しましょう。
- フォントの種類や色の変更が可能か
- 背景画像やロゴの設定ができるか
- ボタンのデザインやレイアウトの調整は可能か
なお、細部までデザインをこだわりたい場合はCSSを直接編集できる機能があるとより理想に近いデザインを実現できます。
また、スマートフォンで閲覧するユーザーのためにレスポンシブデザインへ対応しているかは必ず確認しましょう。
他のマーケティングツールとの連携は可能か
MAやCRMなど他のマーケティングツールとの連携は可能かどうかも、診断コンテンツ作成ツールを選ぶ際に確認しましょう。
マーケティングツールと連携できれば、ユーザーの興味・関心に寄り添ったコミュニケーションを実現し、エンゲージメントや成約率の向上が期待できます。
【確認しておきたいポイント】
- 現在自社で利用しているツールとAPI連携できるか
- CSVファイルなどでデータを出力できるか
導入を検討しているツールが、マーケティングツールとの連携に対応しているかを事前に確認しておきましょう。
料金体系とサポート体制は適切か
料金体系とサポート体制は適切かどうかも、診断コンテンツ作成ツールを選ぶ際に確認しておきたいポイントです。料金については初期費用や月額料金だけでなく、作成できる診断数や回答数に応じた従量課金が発生しないかなども確認しましょう。
無料プランやトライアルで基本的な機能を試し、自社の想定利用規模と照らし合わせて最もコスパの高いツールを見極めてください。
そして、サポート体制も重要です。
特に、初めて診断コンテンツを導入する場合は「操作方法が分からない」「エラーが出てしまった」などの事態は十分に考えられます。上記のようなトラブル時にメールや電話で相談でき、導入時の設定をサポートしてくれるツールは心強い味方になります。
診断コンテンツ作成ツールの費用相場

診断コンテンツ作成ツールの費用相場は、目安として月額数千円〜5万円程度です。機能性や規模によって幅があります。
診断コンテンツ作成ツールの費用は、求める機能やクオリティによって大きく変動します。
まずは自社の目的と予算を明確にしたうえで各ツールのメリット・デメリットを比較検討し、最適なものを選びましょう。
診断コンテンツとは?

そもそも診断コンテンツとは、ユーザーがいくつかの簡単な質問に答えるだけで回答内容に応じて診断結果を表示するコンテンツです。診断コンテンツでは、ユーザー自身がアクションを起こして自分だけの結果を得られるため、高いエンゲージメントを期待できます。
また、ユーザーの診断結果に応じておすすめの商品やサービスを提示でき、スムーズに購買へとつなげられる点もメリットです。
現在では、プログラミング不要で手軽に作成できる診断コンテンツ作成ツールが数多く登場しています。診断コンテンツ作成ツールを活用すれば、HTMLなどの知識がなくても質の高い診断コンテンツの制作・運用が可能です。
診断コンテンツの形式・ロジック

以下では、代表的な診断コンテンツの形式・ロジックを4つ紹介します。
- スコア型
- タイプ分け型
- 分岐型(シナリオ型)
- マトリクス型
各形式・ロジックの特徴を理解し、自社の目的に合った診断コンテンツを作成しましょう。
スコア型
スコア型のロジックでは、各質問の回答に点数を割り振り、合計点に応じて診断結果を提示します。ユーザーの習熟度や知識レベルを数値で可視化するのに適しています。
結果が点数で示されるため分かりやすく、ユーザーも自分のレベルを客観的に把握できる点がメリットです。「資格取得やスキルアップを支援するスクールが見込み顧客のレベルチェックに活用する」などの使い方が考えられます。
タイプ分け型
ユーザーを事前に用意した複数のタイプのいずれかに分類するのが、タイプ分け型です。世の中で最も多く見かける診断コンテンツで、SNSでのシェアを狙う際に特に効果的です。
タイプ分け型では、ポジティブで共感を呼びやすい診断結果を用意し、ユーザーの自己肯定感を満たして「誰かに教えたい」などの欲求を刺激します。BtoCの商材を扱う企業が、ブランドの認知度向上やファンの育成を目的として実施するのに最適です。
分岐型(シナリオ型)
質問への回答によって、次に表示される質問が変わるのが分岐型の診断コンテンツです。まるでユーザーと対話しているかのような、個別最適化された体験を提供できるのが分岐型の強みです。
ユーザー一人ひとりの状況や悩みを深掘りし、最も的確な解決策や商品を提示できる点に長けています。複雑なロジックに見えますが診断テスト作成ツールを使えば、専門知識がなくても比較的簡単に実装できる診断コンテンツです。
顧客の具体的な課題をヒアリングし、最適な商品を提案する際に高い効果を発揮します。
マトリクス型
「質問Aの回答」と「質問Bの回答」というように、複数の回答の組み合わせによって最適な結果を導き出すのがマトリクス型です。価格・好み・用途など複数の異なる軸を掛け合わせ、より精度の高い個別最適化された提案ができます。
取り扱う商品数が多く、ユーザーが自分のニーズに合ったものを探し出すのが難しい場合に最適な選択をサポートする目的で活用されます。
診断コンテンツをマーケティングに活用するメリット
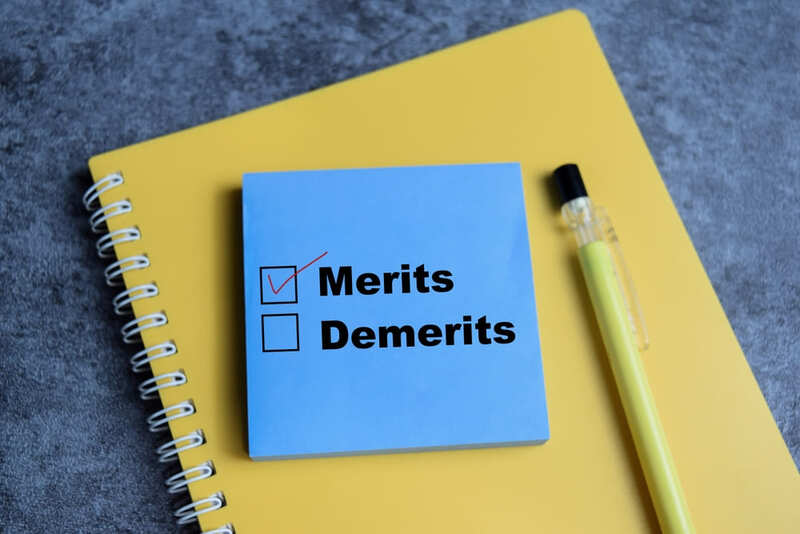
診断コンテンツをマーケティングに活用するメリットとして、以下の3点が挙げられます。
- 見込み客の情報を自然に獲得できる
- ユーザーのエンゲージメントと滞在時間を向上させられる
- SNSでの拡散が期待できて認知度が向上する
診断コンテンツをマーケティングに活用し、認知度の向上や見込み客の獲得を図りましょう。
見込み客の情報を自然に獲得できる
見込み客の情報を自然に獲得できる点が、診断コンテンツのメリットです。診断コンテンツが見込み客の情報を獲得しやすい理由は、ユーザーに「診断結果を知りたい」という強い動機を促せるためです。
例えば「あなたに最適な資産運用プラン診断」のようなコンテンツがあったとしましょう。上記のコンテンツに興味があるユーザーは、自分の将来に関わる有益な情報を得たい一心で回答してくれます。そして「詳しい診断結果をメールでお送りします」などの流れであれば、ごく自然にメールアドレスを入力してくれる可能性があります。
診断コンテンツは「情報を提供する代わりに、結果を教えてもらう」というギブアンドテイクの関係性を自然な形で構築が可能です。そのため、従来のフォームよりも高いコンバージョン率を期待できる点が診断コンテンツの魅力です。
ユーザーのエンゲージメントと滞在時間を向上させられる
ユーザーのエンゲージメントと滞在時間を向上させられる点も、診断コンテンツのメリットです。診断コンテンツはユーザー自身が質問に回答し、次に進んでいく参加型のコンテンツであるためです。
自分ごととしてコンテンツに没入するため、エンゲージメントと滞在時間は必然的に高まります。ユーザーが長く楽しんでくれるサイトは検索エンジンからも価値の高いサイトと評価され、結果的にSEOでの成果向上にも貢献します。
SNSでの拡散が期待できて認知度が向上する
SNSでの拡散が期待できて認知度が向上する点も、診断コンテンツのメリットです。
特に「あなたの〇〇タイプ診断」のようなタイプ分け型の診断はSNSでの情報拡散と非常に相性がよいという大きなメリットがあります。
人は「自分はこういう人間です」という自己表現欲求や「この面白い体験を誰かと共有したい」という欲求を持っています。ポジティブで意外性のある診断結果は、上記の欲求を刺激する絶好の材料です。
診断テスト作成ツールによっては、診断結果の画面にSNSのシェアボタンを簡単に設置できます。ユーザー自身が広告塔となってくれるため、多額の広告費をかけずとも情報が拡散されてブランドの認知度を向上させられる点がメリットです。
診断コンテンツのデメリット・注意点

診断コンテンツのデメリット・注意点として、以下の3点が挙げられます。
- 企画・制作に一定の工数とコストが必要
- 診断ロジックの質が低いと、ユーザーの信頼を損なう
- 公開後の定期的なメンテナンスが不可欠
診断コンテンツを作成する際は、上記のポイントに対して事前に対策を講じておきましょう。
企画・制作に一定の工数とコストが必要
診断コンテンツの企画・制作には、一定の工数とコストが必要な点に注意しましょう。
診断コンテンツ作成ツールの登場によって、診断コンテンツの作成自体は手軽になりました。
しかし、成果の出る診断コンテンツを作るためには、以下のような項目を事前に考えておく必要があります。
- 誰に何を伝え、どう行動してほしいのか
- ユーザーが思わず回答したくなる魅力的なテーマは何か
- 回答と結果に納得感のある論理的な設問とロジックはどう組むか
- ユーザーの満足度を高め、次の行動を促す結果ページはどう作るか
診断コンテンツの作成では、上記の設計を練り上げる工程が最も重要であり、時間もかかります。複数の要素を緻密に組み合わせる必要があるため、制作する際にはしっかりとしたリソースを確保しておかなければなりません。
診断ロジックの質が低いと、ユーザーの信頼を損なう
診断コンテンツは多くのメリットがありますが、診断ロジックの質が低いとユーザーの信頼を損なう点に注意しましょう。
もし、診断コンテンツで提示された結果が論理的に矛盾しているものであれば、ユーザーは企業に対して不信感を抱かれかねません。
質の低い診断ロジックはマーケティング効果がないどころか、ブランドイメージを大きく損なうリスクをはらんでいます。ユーザーが「なるほど」「当たっている」と納得し、満足できるような質の高い診断ロジックを設計しましょう。
公開後の定期的なメンテナンスが不可欠
診断コンテンツがユーザーに長く愛され、安定した成果を出し続けるためには定期的なメンテナンスが欠かせません。市場のトレンド、ユーザーのニーズ、そして自社の商品やサービスは時間の経過とともに変化していくためです。
診断コンテンツを公開した後は、以下のポイントを定期的に確認しましょう。
- 診断結果で紹介している商品が、販売終了になっていないか
- コンテンツ内の情報が古くなって、現状とズレが生じていないか
- ユーザーの回答データを分析し、より良い設問やロジックに改善できる点はないか
診断コンテンツは、公開後の効果測定と改善まで考える必要があります。診断コンテンツを育てる視点を持ち、運用体制をあらかじめ計画に組み込んでおきましょう。
ツールを用いた診断コンテンツの作り方

ツールを用いた診断コンテンツの一般的な作り方として、以下の手順があげられます。
- 目的・ターゲット・ゴール設定などを企画する
- 設問・診断ロジックを作成する
- 診断結果・デザインを作成する
- 診断コンテンツを公開・効果測定する
上記の手順を参考に、利用するツールに合わせて診断コンテンツをスムーズに作成しましょう。
目的・ターゲット・ゴール設定などを企画する
まず、診断コンテンツの目的・ターゲット・ゴール設定などを企画しましょう。どんなに優れた診断テスト作成ツールを使っても、企画が曖昧なままでは期待する成果は得られません。
具体的には、以下の3つの要素を明確に定義しましょう。
| 項目 | 内容 | 項目を設定する際の具体例 |
|---|---|---|
| 目的 | 何のために作るのかを明確にする | ・見込み客のリストを獲得する・SNSでの拡散によるブランド認知度を向上させる・既存顧客におすすめの商品を提案し、購入を後押しする |
| ターゲット | 誰に届けたいのかを具体的にする | ・20代後半の女性で事務職・30代前半の男性で中小企業のWeb担当者・20代後半の男性でITエンジニア |
| ゴール | 何を達成すれば成功かを定義する | ・1ヶ月で新規リードを500件獲得する・診断完了率を80%以上にする・「SNSでのシェア数を1,000件獲得する」 |
上記の企画フェーズこそが診断コンテンツ制作の根幹であり、プロジェクトの成否を決めると言っても過言ではありません。
設問・診断ロジックを作成する
企画が完成したら、次はいよいよコンテンツの骨格となる設問・診断ロジックを作成していきます。設問・診断ロジックの作成で重要なのは、ユーザーが楽しくストレスがかからずに最後まで回答できる体験の設計です。
具体的には、設問を作成する際に以下のポイントを意識しましょう。
| ポイント | 概要 |
|---|---|
| 質問数は5〜10問程度に絞る | 質問が多すぎるとユーザーの離脱につながるため、回答へのハードルを下げる |
| 直感的に答えられる表現を心がける | 専門用語や難しい言葉を避け、誰でも一瞬で理解できる平易な言葉を選ぶ |
| 共感を呼ぶ問いかけをする | 「〇〇なことで悩んでいませんか?」のように、ユーザーの気持ちに寄り添ってエンゲージメントを高める |
設問ができたら、企画フェーズで決めた目的に合わせて診断ロジックをツール上で設定します。
診断結果・デザインを作成する
設問・診断ロジックを組み上げたら、診断結果・デザインを作成しましょう。ユーザーが最も楽しみにしているのが、診断結果のパートです。
診断結果を見たときの満足度が、SNSでのシェアや商品ページへの遷移などの次のアクションに直結します。
ユーザーの心を動かす診断結果を作成するためのポイントは、以下の3つです。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 肯定と共感 | まず「あなたは〇〇タイプですね!」と診断結果を伝え、タイプの特徴をあげてユーザーからの共感を引き出す |
| 具体的なアドバイスの提示 | 診断結果のタイプに向けて具体的なアドバイスや悩みを解決するヒントを提示し、自然な流れで自社の商品やサービスを紹介 |
| 行動喚起(CTA)の設置 | ユーザーにとってほしい行動を促すための明確で分かりやすいCTAボタンを設置 |
また、診断コンテンツのデザインも重要で、自社のウェブサイトやブランドイメージと統一感のあるカラーやフォントを選びましょう。
診断コンテンツを公開・効果測定する
診断結果・デザインが完成したら、診断コンテンツを公開します。そして、診断コンテンツを公開した後は必ず効果測定し、改善を繰り返していきましょう。
多くの診断コンテンツ作成ツールには、分析機能が搭載されています。診断の開始数・完了率、「どの質問で離脱しているか」「どの診断結果が最もシェアされているか」などのデータを定期的にチェックしましょう。
そして、分析結果に応じて以下のように改善策を考えて実行します。
- 「質問3での離脱率が特に高い」というデータが得られたため、当該質問の言い回しを分かりやすく変更してみる
- Aの結果よりもBの結果からの商品購入率が高いため、Bの結果に誘導するロジックを強化する
上記のようにデータに基づいて仮説検証を繰り返せば、診断コンテンツの効果を最大化しやすくなります。
診断コンテンツ作成ツールの運用で成果を最大化させるコツ

診断コンテンツ作成ツールの運用で成果を最大化させるコツとして、以下の3点が挙げられます。
- 診断結果でユーザーに発見と価値を提供する
- 診断結果ページから次のアクションへスムーズに誘導する
- SNSでシェアしたくなる仕掛けを用意する
上記の3点を意識し、診断コンテンツで認知度拡大や売上向上などの成果につなげましょう。
診断結果でユーザーに発見と価値を提供する
診断コンテンツを運用する際は、診断結果でユーザーに発見と価値を提供しましょう。
ありきたりで誰にでも当てはまるような結果では、ユーザーの心は動かずページを閉じられてしまいます。
そこで、以下のように具体的な強みを言語化し、次のアクションにつながるヒントをユーザーへ提示するとよいでしょう。
【例】
あなたは、相手の話を深く聞くことで信頼を築く「傾聴型のコミュニケーター」です。強みをさらに活かすために、次回の会議では、まず3人の意見にじっくり耳を傾けることから始めてみませんか?
上記のように、ユーザー一人ひとりが自分ごととして捉えられる具体的でポジティブなフィードバックを返すのがポイントです。
診断結果ページから次のアクションへスムーズに誘導する
診断コンテンツを作成する際は、診断結果ページから次のアクションへスムーズに誘導する施策も設計しましょう。
診断結果を読み終えたユーザーは、診断コンテンツに対する関心と満足度が最も高まっています。絶好の機会を逃さず、いかにして次のアクションへとスムーズに誘導できるかがマーケティングの成果を決定づけます。
診断結果ページから次のアクションへスムーズに誘導する具体的な施策として、以下のようなものが考えられます。
- 結果に合わせた最適な提案
- 期間などの限定的なオファー
- 関連コンテンツへの誘導
診断コンテンツ作成ツールによっては、CTAボタンを診断結果ごとに調整して設置できる機能が備わっています。診断結果を提示した後には、次のアクションを自然に促すための導線を必ず用意しておきましょう。
SNSでシェアしたくなる仕掛けを用意する
診断コンテンツを作成する際は、SNSでシェアしたくなる仕掛けを用意しましょう。SNSでシェアされれば、ユーザー自身が広告塔となってフォロワーに診断コンテンツを広めてくれます。
ユーザーが思わず「誰かに教えたい」と感じるためには、コンテンツにエンタメ性と自己表現の要素を盛り込む必要があります。
具体的には、以下のような仕掛けを診断コンテンツに取り入れましょう。
- 「〇〇の専門家タイプ」「隠れ〇〇マニア」などキャッチーなネーミング
- 魅力的な診断結果画像の作成
- シェアを促すマイクロコピー
- ハッシュタグの活用
上記のような自然にシェアしたくなる仕掛けを組み込めば、無駄に広告費をかけずとも認知度を高められます。
診断コンテンツ作成ツールを活用したマーケティング成功事例

診断コンテンツ作成ツールを活用したマーケティングの成功事例として、以下の2社を紹介します。
- キューサイ株式会社:スナックのママキャラ診断
- 株式会社ホットリンク(fasme):明日カノ診断
上記の事例を参考に、マーケティングの成果を最大化できる診断コンテンツを作成しましょう。
キューサイ株式会社:スナックのママキャラ診断
キューサイ株式会社は診断作成ツール「ヨミトル」を導入し、スナックのママキャラ診断を展開しました。公開後は完了率90%超、診断回数12,300回超、シェア数5,600回超と想定の約4倍〜5倍の成果を達成しています。
本診断では、ユーザーの心の状態や加齢への感じ方をもとに「オタクママ」「ギャルママ」など多様なスナックのママ像を提示しています。ユーザーの気持ちを受け止め、励ますような新しいセルフケアを提案しました。上記の体験設計により、Xを中心とした拡散が進み、「気が楽になった」などポジティブな反響が多数寄せられています。
参考:キューサイ株式会社が診断コンテンツ作成ツール「ヨミトル」を導入し、話題の「スナックのママキャラ診断」を公開|PRTIMES
株式会社ホットリンク(fasme):明日カノ診断
株式会社ホットリンクの女性向けメディア「fasme」は、明日カノ診断を公開し、累計107万回を超える診断実施回数を達成しています。「fasme」の主要ユーザー層である18~24歳のZ世代の女性が、診断コンテンツに高い関心を持っている傾向を捉えて実施したためです。また、累計発行部数560万部超えの人気マンガ「明日、私は誰かのカノジョ」とコラボレーションした点も人気に拍車をかけました。
明日カノ診断は、質問に答えるだけでユーザー自身が作中のキャラクターでどのタイプに当てはまるのかを診断できるコンテンツです。さらに、診断結果には詳しい結果を解説した詳細記事への導線が設けられており、「fasme」のWebサイト内での滞在時間や他のコンテンツへの誘導にも役立っています。
参考:女性向けメディア「fasme」、累計発行部数560万部超えの人気マンガ『明日、私は誰かのカノジョ』とコラボレーションした診断コンテンツの完全版を公開|PRTIMES
まとめ:最適な診断コンテンツ作成ツールを選んでユーザーを惹きつけよう
診断コンテンツの魅力は、ユーザーが自分ごととして参加してくれる点にあります。売り込み感を出さずに自然な流れでメールアドレスなどを獲得でき、SNSでの拡散による認知度向上も期待できます。
ただし、診断コンテンツを成功させるためには緻密な戦略が欠かせません。まず「誰に、何を伝えたいか」という目的を明確にする必要があります。
現在では、プログラミング知識がなくても本格的な診断コンテンツを作れるツールが豊富にあります。本記事を参考に、最適な診断コンテンツ作成ツールを選んで効果的な診断コンテンツを作成し、認知度拡大や売上向上につなげてください。
発注先の相談は「ITPARK発注エージェント」におまかせ!

発注先を間違えると、成果が出ないだけでなく数十万円の損失になることもあります。
ITPARK発注エージェントでは、BtoBマーケティングのプロが貴社の目的・予算に合う最適なパートナーを無料で選定します。
\簡単30秒で日程調整!/
無料で発注先を相談する